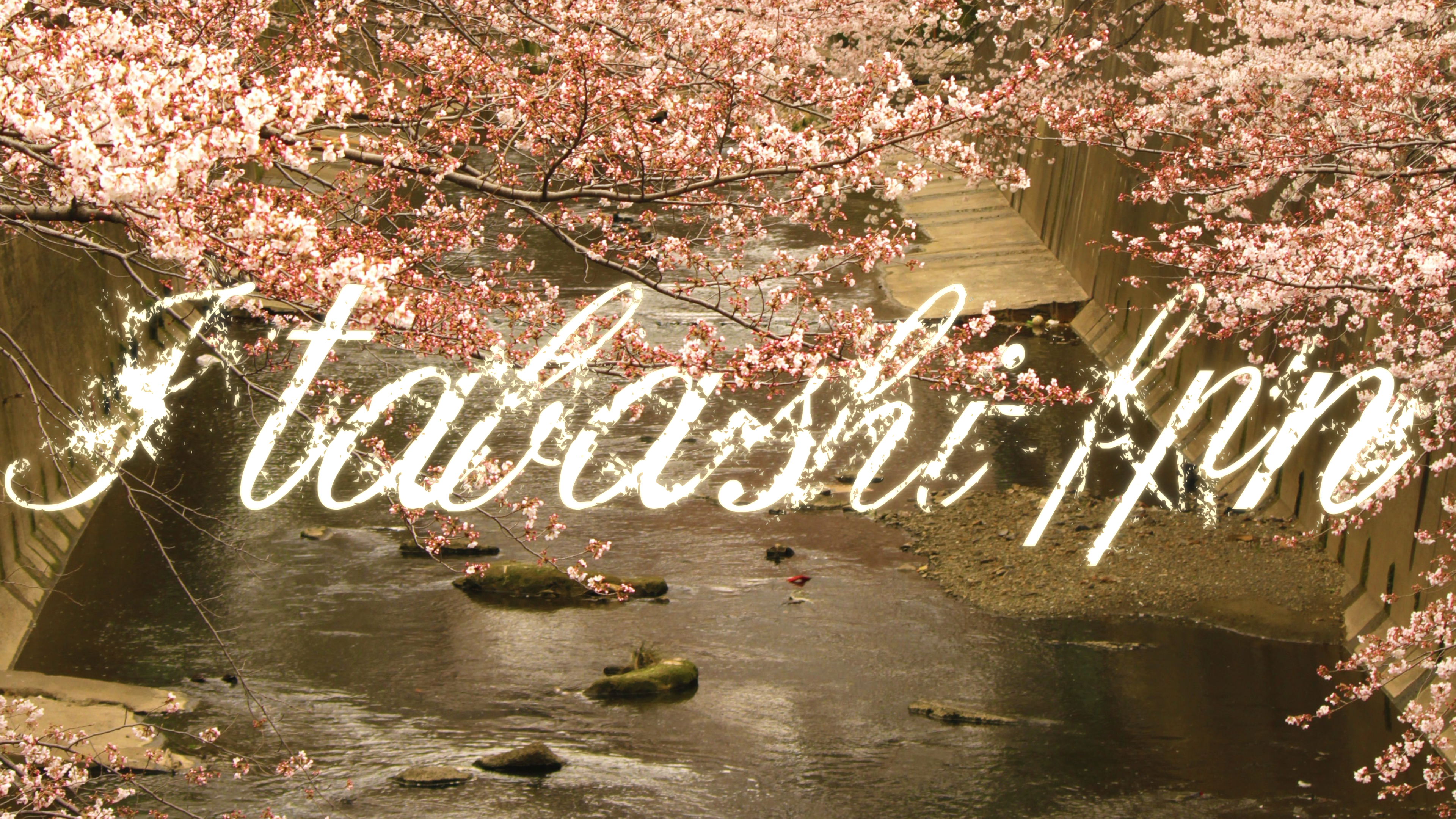↓これで1000字なのバグだろ
私が「道徳教育論」の講義で印象に残ったこととして、講義を受けることによって、自分自身の中にある「道徳」に対するイメージが、どんどん大きく変わっていったということが挙げられる。
毎回の授業課題やコメントペーパーからも分かる通り、私は「道徳」というものに対して、講義当初から非常に懐疑的な姿勢を取り続けた。その理由として、小学生時代に受けてきた道徳の授業が、とても綺麗事ばかりのものであったということ、また私自身がミッション・スクールの中学校・高等学校に通っていたために、「道徳」の単位を「聖書」の単位へと置き換えており、結果として道徳教育を受ける機会もなく、道徳教育に対する印象や価値観を更新することができなかったということが挙げられ、さらには、私が小学校に在籍していたのは9年前のことであるため、小学生6年生時点で平成25年、つまり「特別の教科 道徳」が制定されている現行の小学校学習指導要領の告示(平成29年)以前のことであるということも、理由の一つになりうるのではないかと考えられる。
先述の「特別の教科 道徳」の制定については、平成29年以前の小学校学習指導要領における道徳は、「領域」として扱われていたため、総合的な学習の時間や特別活動と同様に、カリキュラムとしての授業数が明記されておらず、また検定教科書や評価が存在しなかった。しかし、平成29年以降については「特別の教科」として扱われるようになったため、カリキュラムや検定教科書、評価基準などについても定められるようになった。文部科学省(2008,2017)によると、小学校学習指導要領(平成29年告示)第3章「特別な教科 道徳」第3「指導計画の作成と内容の取扱い」3において、教材に関する留意事項が明確に記されているが、一方で小学校学習指導要領(平成20年告示)第3章「道徳」第3「指導計画の作成と内容の取扱い」では、使用教材に関する明確な規定が存在しない。内容についての規定はあるものの、教材に関する統一された基準が存在しないということは、地域や学校によって指導に用いる教材が異なる可能性があるということである。しかしながら、平成29年以降には検定教科書が用いられるようになったことで、日本全国でほぼ同内容の授業を受けることができるようになった。このことからも、平成29年以前とそれ以降では、道徳教育の内容に変化が生じているという可能性が考えられる。