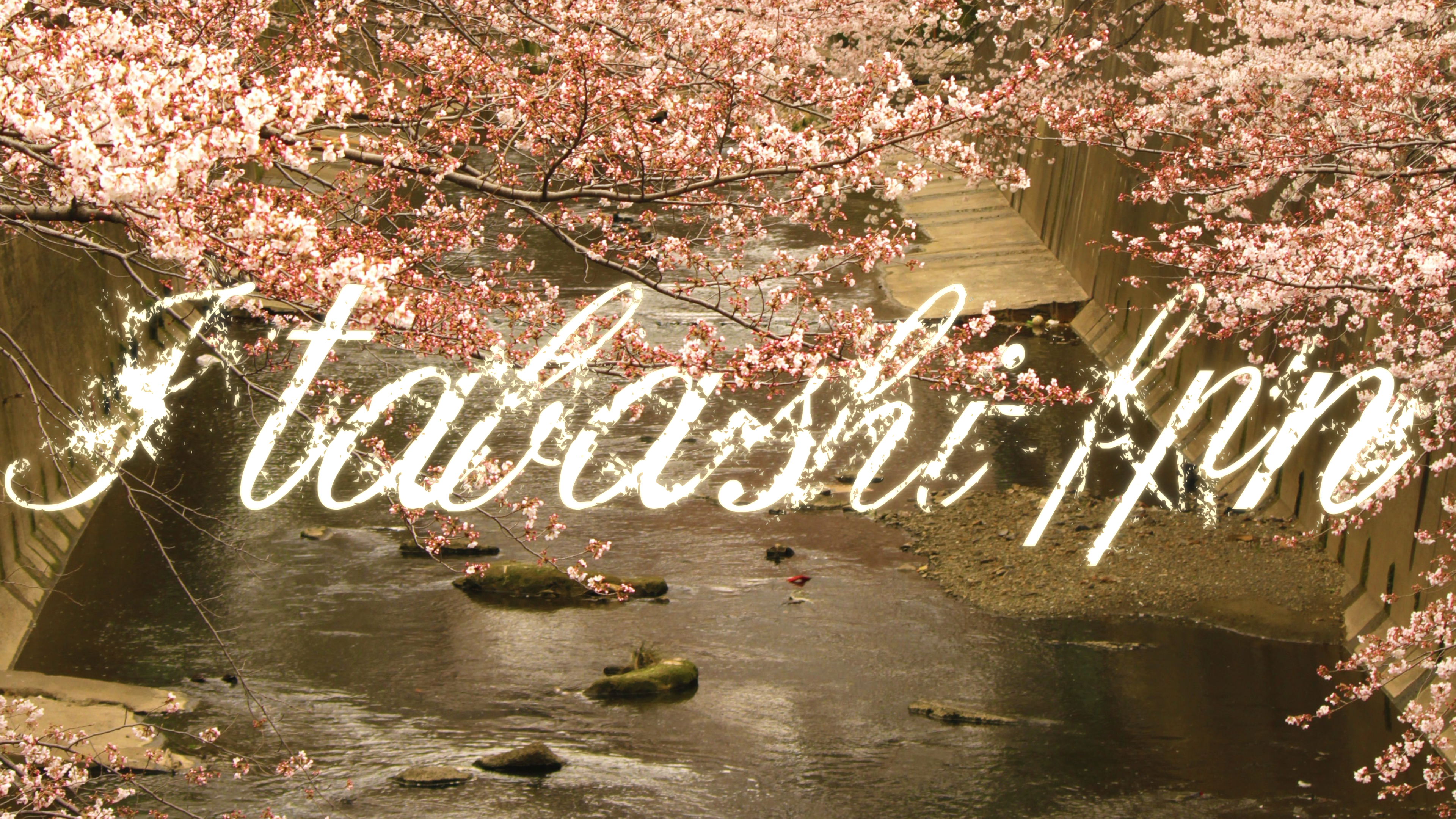レポートの内容(ながい)
本レポートでは、心理的アセスメントⅠで学んだことを踏まえて、知能の理論や研究について述べる。
心理検査の中には「知能検査」というものがあるが、ここでいう「知能」の定義は、研究家たちの間でもいくつかの説があるため、未だに断定されていない。現在提案されている定義の枠組みには、新しい環境に適応する力として適応能力説、新しい行動を獲得していく能力として学習能力説、抽象的に考えたり推理したりする力として高等精神能力説の3つがある。また知能は、ウェクスラー(David Wechsler)によって「個人が目的的に行動し、合理的に思考し、効果的に環境を処理する総合的な能力」と、アメリカ心理学会(American Psychological Association, APA)によって「情報の獲得や経験からの学習、環境への適応、理解、試行や推論の適正な利用を可能にする能力」と、ボーリング(Edwin Garrigues Boring)によって「知能検査によって測定されたものである」とも定義されている。このようにさまざまな説があるが、いずれの説であっても「知能は知的活動に影響を与える要因だ」と抽象的に定義することができる。
知能が具体的にどのような構造をしているかに関する古典的な研究として、スピアマン(Charles Spearman)、サーストン(Louis Leon Thurston)、ギルフォード(Joy Paul Guilford)のものがある。知能研究の先駆者であったスピアマンは、1908年にスピアマンの2因子説を提唱した。これは、知能活動全般に影響を与える要因を一般因子(g因子)と、部分的に影響を与える要因を特殊因子(s因子)と呼び、その存在を主張したものである。一方で、因子分析の発展にも貢献したサーストンは、1938年にサーストンの多因子説を提唱した。これは、知能が言語(V)、語の流暢性(W)、空間(S)、数(N)、記憶(M)、帰納的推理(I)、知覚(P)の、7つの基本的知能因子から構成されると主張したものである。また、ギルフォードは「知能は情報処理能力である」と考え、内容(領域)、操作、所産の3次元から構成されるとした。それらはさらに分割することができ、最終的に知能は100を超える膨大な数の要因から構成されると主張した。
また、16PFなどの性格理論をはじめとして、動機づけや心理療法に関するものなど、非常に多岐に研究を行っていたレイモンド・キャッテル(Raymond Cattell)は、1957年に結晶性知能と流動性知能の概念を提唱した。これはしばしばキャッテルの2因子説とも呼ばれ、一般因子を2種類に分類した上で、過去の経験に基づいた社会規範などの特殊な知識に関する理解力や判断力で、言語的要因との関連が強く、高齢でも維持されやすいものを結晶性知能(Gc, Crystallized Intelligence)、新規場面に適応する際に必要とされる一般的な問題解決能力で、生物学的・視知覚的な要因との関連が強く、20代半ばごろから徐々に低下していくものを流動性知能(Gf, Fluid Intelligence)としたものである。
これらの古典的知能理論の一方で、海外では知能に関する研究がずっと続けられてきており、その中には重要な進展も見られている。例えば知能の遺伝性について、知能は総合的には60%程度が遺伝するとされており、スポーツなどを筆頭とした才能については、遺伝の影響が特に顕著に現れることがわかっている。また、年齢の上昇に伴って知能指数も上昇していく傾向があるといったフリン効果も発見された。
これらの進展の中でもとりわけ重要なのが、キャロルのCHC理論(Cattell Horn Carroll Theory)である。これは1993年頃までに行われた461の知能研究を再分析して得られた理論で、キャッテルとホーンの理論に近いものとなっている。再分析によって特殊因子的要素を持つ16の知的因子が見つかり、そのうちの2つには結晶性知能と流動性知能を含んでいる。これらの16因子にはお互いに正の相関があることから、全体としては一般因子にまとめることもできるとしている。なお、これら16因子は、Quantitative Knowledge(Gq), Reading & Writing(Grw), Comp-Knowledge(Gc), Fluid Reasoning(Gf), Short-Term Memory(Gsm), Long-Term Storage & Retrieval(Glr), Visual Processing(Gv), Auditory Processing(Ga), Processing Speed(Gs), Domain Specific Knowledge(Gkn), Reaction & Decision Speed(Gt), Psychomotor Speed(Gps), Olfactory Abilities(Go), Tactile Abilities(Gh), Kinesthetic Abilities(Gk), Psychomotor Abilities(Gp)によって構成されている。また、16の知的因子があることから、16因子説とも呼ばれている。
他にもガードナーの多重知能理論(Gardner’s Theory of Multiple Intelligences)というものがある。これは「知能は単一ではなく複数あり、人間は誰しも複数(8つ)の知能を持っている」という仮説であり、g因子の存在を重視せずに個人の特徴に応じたアプローチをすべきだと主張するものである。しかしながら、これは実証的な研究に基づいていないと批判されることもある。これらの8因子は、対人的知能、論理・数学的知能、博物学的知能、視覚・空間的知能、内省的知能、言語・語学知能、身体・運動感覚知能、音楽・リズム知能から構成されている。